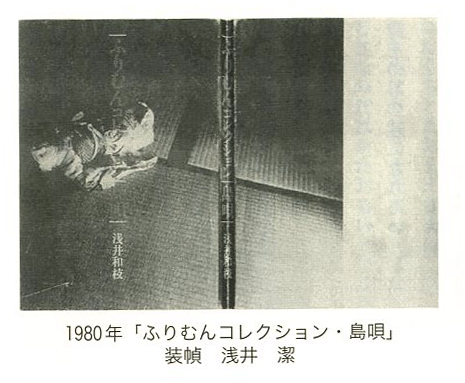(五)「ふりむんコレクション」─自死願望を鎮魂するために書かれた「ふりむんコレクション」
私は「月曜日の兄弟たち」が好きで、干刈あがたにしか書けない作品だと思っている。もし彼女が生きて、干刈文学の代表作を書くとしたら「月曜日の兄弟たち」のような、時代や歴史に寄り添って“見る“役を自分に振って書いた叙事詩のようなものではなかったかと思う。この時代や歴史に憑くように“見る”という巫女的な特質は、干刈あがたが幼少女期からの自死願望を辛うじて抑止した結果得た、特殊な能力だと考えられる。「ふりむんコレクション」には干刈あがたが自らの自死願望と向き合い、戦っている姿が収められている。あるいは、自らの自死願望を鎮魂するためにだけ書かれたのが「ふりむんコレクション」だったのではないだろうか。
「ふりむんコレクション」は
Ⅰ 島
Ⅱ 青梅町
Ⅲ 夜
Ⅳ ふりむん経文集
から成っている。
Ⅰ 島
「島」は“ミミ”と“西原(にしばる)ヤンバ”という南島の民話風の五行と十一行の短文である。寓話でもなく昔話でもない、物語としては中途半端なふたつの断片をどのように読んだらいいのか。なぜこの二文が冒頭に必要だったのか。短い文章なので再録する。
ミミ
ユクミのミミと呼ばれる男が道を歩いていると、それはほとんど止っているように見えた。 ミミは道のどんな小石も、足で一つ一つ踏まなければ前へ進めないので、村はずれの畑へ行くだけで半日かかってしまう。
おとなしい女房と息子がいて、ミミのかわりに黙って働いていた。九歳ほどの息子は、髪も肌もすきとおるような白子(しらこ)だった。ミミの一家は息をひそめるように暮していた。
西原(にしばる)ヤンバ
島の港に船が入ると、ヤンバは下船した人の荷物を持って家までついて行く。それでわずかな労賃を稼いでいたが、届け先の家で一食の飯と酒をふるまわれると、よろこんで庭先でうたい踊った。その唄は「ウーヤーヌ ヒトゥヒトゥサー」という言葉を単調にくりかえすだけで、その意味は誰にもわからなかった。その踊りは、手足がバラバラに跳びはねるような踊りだった。
ヤンバには西原に家があった。ふだんは何事も起こらないのに、ヤンバが家に帰るとかならず何かが起こった。ある時は姉が夜中に叫び声をあげて家からとび出し、翌日浜に死体があがった。ある時は父親が首を吊った。だからヤンバは家に帰らないのだった。けれど、時々母親がそっとヤンバを家に連れ帰る。するとまた、一番下の弟が木から落ちてケガをし、破傷風にかかって死んだりした。そうしてヤンバの家はだんだん衰え、最後には母親一人になってしまった。もうヤンバは決して家に帰らなかった。
「ふりむんコレクションⅠ」
この短い民話風の二つの断片が「ふりむんコレクション」の冒頭に置かれた理由を想定するとしたら、〈民話〉が民話であるための文体には、村落共同体に何層も堆積した“死”が隠されているということである。たとえば、「ミミの一家は息をひそめるように暮していた」という一行の背後には、何世代にも亙った無数の家族の離散や廃絶や逃亡が隠されている。あるいは逆に、“西原ヤンバ”のように村落共同体内部の数え切れない非業の死や不慮の死、狂気を一家族の出来事に昇華させて語られる場合もある。民話風の冒頭の二つの断片は、民話の文体が内包している“死”を、干刈がたの自死願望が察知して無意識に置かれたものだと考えられる。
Ⅱ 青梅町
「青梅町」は、五つの詩と十二の短文で、干刈の幼少女期の“原風景”が表現されている。幼少女期の回想ではなく、原風景であるというのは、それらがどれも〈民話〉風の断片へ昇華される要素を含んでおり、詩にも短文にも“死”が隠蔽されているということである。ここで干刈は、幼少女期の暗く辛い個別的な体験=〈自死願望〉を青梅町という共同体内のさまざまな〈死〉に重ねて表現しようと試みている。
“ふがふがよっちゃん”は自由詩でありながら五七調の定型が意識されている。それは干刈が幼少女期を直視しようとした時、言葉にできないほど暗く辛い想いを、定型という衣を纏うことによって、村落共同体の暗さや閉塞感にうまく同調・同化して表白することができたからである。
ふがふがよっちゃん
1
ひゅる ひゅる
御岳の山おろし
青梅街道吹きぬけた
青梅夜具地は何反織れた
ふがふがよっちゃん
綿入れはんてんも着ねえで
ふらふらどこへ吹かれて行くんだんべ
2
ユキノシタの毛ば毛ば葉っぱ お皿
ナズナの花 おこめ
梅のこぼれ花 ご馳走
ふがふがよっちゃんはお雛様
ただぼんやり坐っている
3
山つつじの花喰いながら
裏山道を分け登る
一列に並んだ子供たち
頭一つとび出して
遅れて行くのがふがふがよっちゃん
子供七つ八つよっちゃん十二
4
西分の住吉神社の祭礼五月
お母ちゃん行商の夜具地は何反売れた
十円・・・・・・くんねえか
十円で買えるもの
おはじき ビーズ玉 ままごとの急須
海ほうずき ハッカパイプ モール
針の糸とおし(お母ちゃんに買ってやりてえけんど
おれのが買えなくなる)
なんでもよく光る磨き粉
「何者の祟り何者の執念で斯様な姿に生まれたか
親の因果が子に祟り」
見世物小屋は外からのぞくだけ
ふがふがよっちゃんのお母ちゃんが
いつか泣いていたことがある
わたしら夫婦はイトコどうしだと
血が近すぎた親の因果だと
5
しるしる雨に梅の実落ちる
ひろって喰ってはいけねえよ
青い梅には毒がある
6
あれ
機屋の糸くずだんべえか
しろっこだんべ
ああ しろっこだ
しーろっこ しーろっこ
こっちいとんでこい
ふがふがよっちゃんよお
材木置場でズロースぬがされて
おへそに
梅の種入れられたんだとよ
しーろっこ しーろっこ
こっちいとんでこい
7
きらきら砂金は
多摩川かわら
くねくね蛇行は
多摩川ながれ
青梅のこどもは
多摩川カッパ
ふがふがよっちゃん
白いももから赤い血ひとすじ
8
御岳の紅葉は
あか きい ちゃいろ
夜具地の糸も
あか きい ちゃいろ
9
ふるふるこゆき
御岳のお山は見えなくなった
ふがふがよっちゃんも見えなくなった
ふがふがよっちゃん
どこへ行ったんだんべ
お山の嫁さんになったんだんべえよ
“ふがふがよっちゃん”とは「Ⅱ青梅町」に収録されている“あんども屋”の姉妹弟の姉のことだと思われる。「Ⅱ青梅町」に収録されている断片集をつなぎ合わせてつくられた小説「真ん中迷子」では、“あんども屋”の母親は行商中に殺害され、リヤカーとともに「街道からはずれた林の中で発見された。三人の子供たちは青梅には孤児院がなかったので自動車で北多摩の児童ホームに連れて行かれた」となっている。ここでは「ふがふがよっちゃん見えなくなった お山の嫁さんになったんだんべえよ」という民話風の結びになっているが、定型的な結びとして読むのではなく、つまり、「お山の嫁さんに」なりたかったのは干刈自身であったというように、干刈あがたの自死願望が“ふがふがよっちゃん”一家の廃絶に仮託され、重ねられて表白されているというように読むべきだと思う。暗く辛い干刈の幼少女期の体験は、あんども屋の母親の非業の死や子供たちの離散に重ねられることによって、はじめて吐露することができたのである。幼少女期の干刈の原風景を辿っていくと、何日も何日も一人で留守番していると“さびしくて”死んでしまいたいくらい怖かった体験があり、また誰からも庇護されない孤独をただ“真ん中にいるとだけ感じている”感覚へと遡ることができる。それらが原風景の核心部分だったと考えられる。
「Ⅱ青梅町」に収録されている他の詩や短文が、村落共同体の暮らしのどんな出来事どんな不幸に干刈の自死願望が同調・同化しているか見てみよう。
“路上” 「ヌキューチ」子供たちの間に無言の電令が走った。それが織物で立つ町の、税務署だか経済警察だかの抜き打ち検査だった。
早く駅についたのは電車で、(大学生と駆け落ちする妻を追いかけたが間に合わず)上田さんはとり残された。コツコツと義足の音を響かせて、上田さんは子供たちの路上を横切り一人で帰って行った。
“ササキ” ササキは老いて死んだ。けれどやはり子供たちは、崖下の道を通る時は走った。
“松” 一本松はその後“首吊り松”と呼ばれるようになった。
“裏道” “脳天ファイラーの○○○○”
“早春” 白いカッポウ着をつけた近所のおばさん達の背中ごしに、妹は部屋の隅で見ていた。蒲団に横たわっている兄の足に、母親が足袋をはかせているのを。その足袋の白さを、小ささを。横に置かれている棺も小さかった。
“金魚” メカケの子はときどき路地で金魚鉢の金魚を見ていました。冬は金魚が死んでしまっても路地で金魚鉢の水を見ていました。金魚鉢は母親を囲っている男が来ているという暗号でした。
“石鹸問屋へお嫁にいった綾子さん” 綾子さんは石鹸問屋から戻ってきた。石女で神経衰弱になったのだという。ヒマラヤ杉の下で会っても、もう何も言ってくれなかった。
“少年ケニア” 「死んでもいいから飛行機見せて」少年ケニアの載っている雑誌は、ようやくまわってきたけれど。
“くの字くの字” ところがある日両親がちょっと眼をはなしたスキに、太郎はタライの中に頭から落ちてしまいました。タライだから水の深さはたいしたことなかったのに、嘘のように顔を水につけて溺れ死んでいました。
“色硝子” 母親は手放してきた瑪瑙と翡翠を歎く。けれど少年が所有したものは、あまりにも美しい過去だったので、もう未来を語ることもできない。
“お次の番だよ” シズエは、夜、眠るのが怖くてたまらなくなった。眠るまいと眼を見ひらいて、ふとんお中でいつまでも起きているようになった。そうすると、天井の闇のあたりに白いものが動くのが見えはじめる。ドンツクドンツク。ドンツクドンツク。
“裸足” ナルセは走った。ある時は裸足でタンポポを踏み、ナズナを踏み、オオバコを踏み、桑畑をかき分け、桑の枝を曲げ、桑の枝にしっぺ返しをされ、菜の花の蕾をひきちぎってかっ喰らい、ハコベを踏み、葱坊主の頭を蹴とばし、日向和田の踏切を渡り、吉野の梅郷の梅の下に立っていた。
“真ん中” 「世の中には奥行きと方向、高さ低さがあるだろう」もう「わからない」とは言えないから、女の子は黙っていた。女の子はただ真ん中にいるとだけ感じた。
父親が出現するあたりが暗くなるのも、母親が出現するあたりが温かくなるのも、ただ受け入れた。女の子は真ん中にいたから。
“あんども屋” あんども屋はなんでも屋だった。なんでも売る。からだも売る。
“二人” 子供たちは男から歌も習った。「こころのなやみを、つつまずのべて、などかはおろさぬむねのおもいを」というのだった。
“道行き” 母親は噂の出所を求めて訪ねて行く先は、だんだん遠くなっていった。女の子は下の子を背負った母親に連れられて、毎日街道を往復した。見知らぬ家の玄関に立つ時、女の子はふるえた。
「ふりむんコレクション Ⅱ 青梅町」
自らの自死願望を抑止するために、干刈がこれらの事件や狂気や不幸に同調・同化するのは、無意識の自己防衛本能だったと思われる。つまり、幼少女期の干刈は、自分の暗くて辛い想いを慰めるために、自身の不幸や悲惨さと同様な不幸や狂気や悲惨さを、村落共同体(青梅町)の暮らしの中から抽出して、自己同化することによって自己救済していたのである。そしてまちがいなくここに、干刈あがたの時代や歴史に憑くように“見る”という作家としての特異な能力の秘密があったと考えられる。
単行本『樹下の家族』に書下ろされた「真ん中迷子」は、「Ⅱ青梅町」のこれらの断片をつなぎ合わせて書き直されたものである。題名の“真ん中迷子”とは、干刈あがたの幼少女期の自死願望そのもののことではなかっただろうか。「真ん中迷子」には、干刈あがたの自死願望がどのように形作られていったのかが書かれている。
「世の中には奥行と方角、高さ低さがあるだろうが」
もう「わからない」とは言えないから、黙っていた。文恵はただ真ん中にいるとだけ感じていた。そうした種類のことで父親が文恵に焦立つのは、初めてではなかった。
駅の改札口の手すりにつかまって母親の帰りを待ちながら、単線鉄道の二本のレールをみていると、文恵はもう母親が帰ってこないのではないかという気がすることがあった。
一人で眠る文恵には、ほかにも怖いものがあった。〈紫色の着物と白足袋〉は、一つ違いのすぐ上の兄の伸二が百日咳で死んだ時の、かすかな記憶であるらしかった。
文恵は夜、眠るのが怖くてたまらなくなっていた。眠るまいと蒲団の中で眼を見ひらいていると、天井の闇のあたりに白いものが動くのが見えてくる。ドンツクドンツク、ドンツクドンツク。叫び声をあげそうになる瞬間、気を失うようにして眠りに落ちた。
「おとうちゃん」と文恵は言った。「夜がねむられないの」
「そんな言い方はないだろう。夜ねむれないの、だろう」
父親は言い方を直させただけだった。文恵は訴えたいことがまだ沢山あったが、また言い方を間違えるかもしれないので黙っていた。
そして「真ん中迷子」は次のような自殺未遂を暗示させる描写で結ばれている。
通勤電車の前照灯がどんどん近づいてきて、その明りと十文字に交叉する瞬間、文恵はふと体が揺れてふわりと浮き上がったような気がした。その時「文恵」と強い声がして、肩がしっかりつかまれた。文恵の肩をつかんだアヤの手には、痛いほど力がこもっていた。
「真ん中迷子」結び
「真ん中迷子」は青梅町内に起こった狂気や事件や不幸のエピソードを挿入しながら、幼少女期の干刈のなかに自死願望が形成されるまでを描いた作品だったということができる。
Ⅲ 夜
「夜」は思春期を迎えた干刈の短い独白体の散文集である。干刈あがたの自死願望は一層はっきりとした輪郭をもつようになる。
“十三歳”
その少女は死にたい子供だったかもしれない。二つの時に耳の手術。六つまでは腫物だらけ。
八つの時に眼病みの手術。九つの時に喉の手術。十二の時に鼻腔の骨を削る手術のノミとツチで叩く音は、手術を受けながら数えた。十三の時に開腹手術。一つ一つに病名がついていたけれど、それは死にたい心の全身症状であったのではないか。
少女が血を吐いた日、母親は櫛をポキリと真ん中から折った。その櫛は母親がどこかでひろったものだという。櫛は苦と死なのだから、こんなものをひろったお母さんが悪かった、ごめんね、と言ってポキリと折った。少女はその母親の何かひどく強い力が怖かった。なぜ母親はひっそりと見えないところで、櫛を捨ててしまわなかったのだろう。その強い力が、少女を死にたい子供にさせたかもしれない、ということはないだろうか。
少女は退院した。けれどわけのわからない不安に駆られて、ひどく胸がドキドキして、あまりの動機のはげしさに息苦しくなり、うずくまることがあった。
牛乳を飲むと、かならず吐いた。ニンジンとほうれん草は喉にひっかかり、やっとのみこむと胃が裏返りそうな吐気がこみあげた。
少女は、体というものが怖くて怖くてたまらなかった。初潮の時に血が止まらなくなって死ぬのだと思いこんで、その日を待っていた。
「ふりむんコレクション Ⅲ 夜」“十三歳”部分
「Ⅲ夜」のなかの他の散文は、「Ⅱ青梅町」と同じように事件や狂気や不幸に思春期の干刈あがたが同調・同化した時書かれている。戦後の混乱期の青梅町から戦後復興を終えた東京郊外の新興住宅地の日常のなかの出来事へと同調・同化する対象もシフトしている。「Ⅱ青梅町」では戦後の混乱のなかで、事件も狂気も不幸も濃密なリアリティーを持っていて、干刈はそれらに同調・同化するだけで自分自身を慰められた。しかし戦後復興したことによって、かつては確かにあった濃密なリアリティーは拡散し、「Ⅲ夜」の散文は干刈の自死願望を満足に受け止めきれていない印象をうける。そして、慰撫されない分、“十三歳”のような自らの自死願望をストレートに表白した文章を書いて、バランスをとったのだと思われる。
「Ⅳふりむん経文集」
「ふりむん経文集」は、干刈あがたが自身の自死願望を克服した後、自らの幼少女期をふり返って鎮魂するために書いたものと、破綻しかかった結婚生活の末期に精神的に追い詰められて、かつての自死願望がよみがえって現出した時に書かれたものがある。
童(わらべ)経
眼えつぶれ
動くな
死め
死んだふりごっこすると
いつもさいごまで死んで
いられたのが童(わたし)です
骨骨(こつこつ)経
生身の人ゆえ血がぽとり生身の人ゆえ涙がぽとり生身の人ゆえうめきごえ
生身の人ゆえのしかかる生身の重さにひしがれて考え出したさびしい遊び
人はみな骸骨
泣いてる骸骨ハナかむ骸骨食べる骸骨靴はく骸骨風呂をわかして入る骸骨
父親骸骨母親骸骨長男骸骨長女骸骨次女骸骨カタカタ震える骸骨だんらん
人と人とがぶつかれば骨骨骨人と人とが抱合えば骨骨骨人間木魚で骨骨骨
全く解説や説明がいらないほど、直截である。言葉にするのが辛いほど幼少女期の内部世界として残酷である。
小さな経
小さな木の実がすき。
お茶の実。珠数玉。南天。青木。
椎の実。ドングリ。からすうり。
山葡萄。桑の実。木いちご。名
も知らぬだいだい色の小さな実。
ぐみの実。ころり。掌の上でこ
ろがせば何だか気持が落ち着く。
小さな経。「南無ころころり」
さびしくて眠れない毎日のなかで「掌の上で小さな木の実をころがして」いる時だけは「気持が落ち着く」のである。
十四歳の曼陀羅華(まんだらげ)全行
私 眠れない 私 ずっと 眠っていない 夢ばかり見る とぎれ とぎれに 影 あれは
何 白い鳥 のようなもの 私の窓辺 かすめて翔ぶ 声 聞こえたの ほうせんか はじけ
るような 小さな子供の 笑い声 鳥 いつのまにか 私 鳥 胸やわらかく 卵を抱いて
うずくまる 喉 おしひろげ 私 叫ぶ 声がでない ………… ………… また 聞こえる
の ほうせんか はじけるような 小さな子供の 笑い声 私 笑っているの 私 かしら
私の中に 見知らぬ誰か いるみたい 髪 ふるわせて もがきながら すいこまれてゆく
葡萄色の 夜明けの空
干刈あがたの年譜では「杉並区立中瀬中学校に入学。中学時代は学年の首席を争う成績だった。家が下宿を兼ねるようになって、本は下宿の学生から借りた。探偵小説、短歌、社会主義の本などを乱読する一方、吉屋信子の少女小説にも夢中になった。少ない小遣いをためて買ったツルゲーネフの『初恋』や与謝野晶子の『みだれ髪』は一行一行味わって読んだ。音楽ではプレスリーの歌に夢中であった。彼のファンであった音楽の先生が放課後にプレスリーのSPを聴かせてくれた」とある。しかし十四歳の干刈あがたは、かなり危ういところにいたのである。この詩は、ひとつまちがえばかなりの確率で“この世とおさらば”しかねない危うさを隠し持っている。
思春期の干刈あがたの〈生〉を此岸に引き留めたものは、干刈の唯一の黄金期であった高校生活であったと思われる「干刈あがた再論三(「雲とブラウス」論)」でも取りあげた“初陣の加持”は、「ふりむんコレクション」のなかでここだけが明るく輝いて異彩を放っている。
初陣の加持
わが十七の初陣に キリリと眉を吊り上げて
処女(むすめ)なり
さればこそ意気は弓なり 裸身一つを矢とつがえ 君が胸を射んとゆく。
君十八の春の陣 ふるえる唇ひき結び
男子(おのこ)なり
さればこそ討死にもよし しろきみ胸に矢を立てて 朱の血潮に染まるなり。
この“初陣の加持”と「Ⅲ夜」のなかの“月光”を読むと、十七歳・思春期の干刈の最良の部分を理解することができる。
月光
月明かりの夜だった。
十四歳の妹娘はもう眠っていた。
十七歳の姉娘は、風呂から上ってくると、電灯を消し、鏡の前に立ち、衣はらりと脱ぎすて、
月の光を掌に受け止めるように腕をかざして、鏡の中の自分の裸身を見た。
その時、くすくすと笑う声が聞こえた。姉が妹をふり返ると、妹はやはり眠っている。眠った
まま妹は身をのけぞらせ、くすくす笑っていた。むき出しの喉に、白い月の光が刺さっていた。
しかしこの二篇から想像できる黄金期の体験を経ても、干刈は内部にある自死願望を消去することができなかった。干刈が自らの内部の奥深くに保持しつづけてきた自死願望をほんとうの意味で克服できたのは、病気治療のため上京していた伯母を送り届けるために、はじめて沖永良部島に渡った二十歳の時であったと考えられる。「島唄“暗い唄の旅”」や「入江の宴」にはその時の解放感が素直に描かれている。「Ⅳふりむん経文集」では、“故里賛”がその部分であり、散文の“暗い唄の旅”を詩で表現したものである。
故里賛
故里は 常闇(トコヤミ)の国
双性の巫 司る御獄(ウタキ)
犬神(イヌガン)と契りし女神(オンナカミ) 国祖(クニオヤ)の島
十七乙女(ミヤラビ) 蛇神(アカマタ)の子を生みし岩屋
浄(キヨ)ら祝女(ノロ)ら遊女(ズリ)なり 盗人狂人殺人者を慰める里はずれ
女なべて神にして 月の光に舞い狂う里
大木の葉群ざわめき 死者神下(ハミサガ)る庭
生者と死者との合歓のあえぎ ゆらめきのぼる褥(シトネ)
故里はこの身深く 泉わく暗川(クラゴ)
秘かに秘かに 火神(ヒヌカン)を見るものぐるい
この時以後、干刈あがたは切迫した自死願望からひとまずぬけ出したと考えられるが、それ以後も精神的に追い詰められると資質的な自死願望がくりかえし現れることになる。それは切迫した危機というより、自覚された自死願望であったと思われる。
夫の浅井潔氏が装丁された私家版『ふりむんコレクション・島唄』の表紙にもなった“少女の部屋への鎮魂歌”は、自覚された干刈あがたの自死願望が表白されたものとして読むことができる。
少女の部屋への鎮魂歌(たましずめ)
うすあかり うすくらがりの部屋の中
少女が人形抱いている
人形よくよく見てごらん
それはほんとの赤ん坊
うすあかり うすくらがりの部屋の中
少女が赤ん坊抱いている
赤ん坊よくよく見てごらん
人形みたいに死んでいる
うすあかり うすくらがりの部屋の中
少女が死んだ子抱いている
少女よくよく見てごらん
眼から涙こぼれてる
うすあかり うすくらがりの部屋の中
少女が涙をこぼしてる
涙よくよく見てごらん
ニセ細工師のガラス玉
うすあかり うすくらがりの部屋の中
少女の涙はガラス玉
ガラス玉よくよく見てごらん
少女と死んだ子うつってる
うすあかり うすくらがりの部屋の中
少女はいったいどこにいる
部屋をよくよく見てごらん
少女は鏡の中にいる
うすあかり うすくらがりの部屋の中
ほんとの少女はどこ行った
少女王国ぬけ出して
母たちの国へ行きました
この詩は、母親となった干刈あがたの赤ん坊を抱いている姿が鏡に映っているところからはじまり、人形→赤ん坊→死んだ子=幼少女期の自分自身というように数珠つなぎになって連想されていき、幼少女期の自死願望をもった自分は「(子を産んだことによって)少女王国ぬけ出して 母たちの国へ行きました」という鎮魂歌になっている。「少女と死んだ子うつってる」とは、幼少女期の自死願望をもった少女とその少女が大人になった自分の姿のことであり、それはまた母親となった干刈あがたの中にも、いまだかつての自死願望が漂流しているという表現にもなっている(詳しくは「干刈あがた再論(十一)」。
母親になってからの干刈あがたの自死願望は、一層自覚的に制御・抑制されたようであるが、離婚前の精神的に錯綜した状態になると、にわかに自死願望がせり上がってくることになる。
ややこはくらいくらいやみからうまれたのでこんなにひかりにみちているのですか。中略
どうぞこのこがおおきくなるまではわたしをやみにつれもどさないでください。
“子守り呆け経”部分
「人は死んだらとりかえしつかぬ」
いいえ
人は生んだらとりかえしつかぬ
生んでしまった
こうもかわいいものを
こうもうつくしいものを
こうもいとしいものを
ひとりでふらりこの世から
いちぬけたすることもできなくなった
「親が子をまもる」
いいえ
子が私の命をつかまえていてくれる
“子をとろ親とろ子ぼんのう親ぼんのう”後半
これは自覚的に制御・抑制されている結婚生活前半の時期だと思われる。
今日の経(いつかゆきたい)
やみにひかれるみなればこそ
いつかゆきたいばしょがある
さいほうじょうどはしらぬこと
しこくなのはなうみべのみち
それよりあわくありやなしや
ほのかなひかりゆれるばしょ
まいりましょうかといわれたら
きよらかにただひとこと
まいりましょうとこたえるために
たとえばきょうならにがつようか
いちにちさんどのめしをつくり
たろうじろうをだきしめて
ときにはしりなどひっぱたき
あいしているやらいないやら
ありがたいやらたくないやら
ながねんくらしたおまえさまに
こんやもやはりふろをたて
ときどきなみだはかたおもい
すきなうたなどくちずさみ
すきなほんなどよみながら
いってしまえばかんたんなひび
やみをみるなやみをみるなと
となえつついましばらくは
このよのくらしつづけます
これが私家版『ふりむんコレクション・島唄』を出版した一九八〇年・三十七歳頃の干刈の自死願望の率直な姿である。「Ⅳふりむん経文集」の最後におかれた“辻にいて”は、自死願望を消し去ることができないことを自覚した干刈あがたのその頃の“自分の理想の姿”であったと思われる。
辻にいて
いつかなり
たい女人像
童女と聖女
聖女と遊女
遊女と童女
こきまぜた
辻かんのん
辻こつじき
辻のあほう
この身そのもの辻になりたい
「ふりむんコレクション」Ⅰ島、Ⅱ青梅町、Ⅲ夜、Ⅳふりむん経文集を干刈あがたの自死願望に焦点を当てて辿り、考えてきた。干刈あがたが自死願望を抑制・慰撫するために編み出した共同体内の事件や狂気や不幸に同調・同化する資質が、琉球諸島の姉妹(ヲナリ)神的資質に重なることによって、時代や歴史あるいはものや人に寄り添って“見る”という作家としての巫女的な特異な才能に転化されたのだと考えられる。この“見る”という役割が、宿命のように自分に振り当てられていることを、干刈はかなり早くから自覚していたようである。
「月曜日の兄弟たち」は作家・干刈あがたがはじめて“見る“役を、それこそ姉妹(ヲナリ)神そのままに兄に寄り添って行使した作品であり、また見事に時代を俯瞰した作品になっている。「月曜日の兄弟たち」の前振りのつもりで書き始めた「ふりむんコレクション」と干刈あがたの自死願望についてが、意想外に長くなり、一文とした。引用文が多いのは、私の干刈あがたの自死願望を想定した「ふりむんコレクション」の理解の仕方を、いっしょになって確認してもらいたかったからである。
二〇〇五年十一月二三日